
こんにちは!ビズキャンプラス運営の畠中です。
今回は、Happy Quality株式会社代表 宮地誠 様へインタビューさせていただきました。
「生産から流通までの世界のスタンダードを作る」をビジョンに、アグリテック技術の研究開発と八百屋事業を展開するHappy Quality株式会社。農業のDX化を推進し、世界でも注目される技術開発を行っています。
今回のインタビューでは、事業内容や独自の強み、農業界への挑戦、そして学生へのメッセージまで、熱い思いをたっぷりとお届けします!
「農業ビジネス」「アグリテック」「起業」などに興味のある方、必見です!
会社概要
会社名 Happy Quality株式会社
代表 宮地誠
住所 静岡県浜松市中央区飯田町1567-1
静岡県袋井市久能1887
設立年月 2015年2月13日
事業内容 農業Al技術を用いた製品開発・コンサルティング業及び野菜卸業
URL Happy Quality株式会社
インタビュー
(鈴木)
まず御社の事業について説明をお願いします。
(宮地さん)
弊社は静岡県で事業を営んでおり、仕入れて売るという八百屋の事業が売上全体の7割を占めています。そして、弊社がスタートアップと言われる所以になったのが、アグリテック、農業のテクノロジーの研究開発です。植物の顔色を伺うという実数値、ドラえもんの世界でしかできなかったようなことを研究開発しています。ここは世界でも負けない自信があります。あとはDXという力を用いて、生産から流通までを一貫する、世界のスタンダードを作るというビジョンのもとに活動している会社です。

(鈴木)
ハピトマ、ドクターメロンは、どのような商品ですか。
(宮地さん)
ハピトマは中玉のフルティカという品種のトマトです。我々独自の栽培手法で高品質で高機能かつ機能性表示食品の認可を取って流通しているのがハピトマというブランドです。
ドクターメロンは、メロンってカリウムが多いがゆえに、透析の方や腎臓疾患の方が食べれないんです。果物の王様マスクメロンを求めやすい価格で、食べれない方がいるならば食べれるものにしたい、要は食のストレスをなくしたいという思いで開発したのがドクターメロンです。
(鈴木)
御社にとって、他社と差別化している一番のポイントを教えてください。
(宮地さん)
本質の話をさせていただきます。農業界では、「栽培する農家さん」「再現性を高めるための技術開発(アカデミックな研究開発)」「流通の部門」この3つがあって農業の世界が動いています。私たちが絶対に負けないのは、この3つを1つで捉えている会社だということです。これは日本ではうちしかないです。なのでうちの敵対会社は農水省。そこが最大の強みです!
(鈴木)
DX化やスマート農業の導入を進める中で、一番大きなハードルは何でしょうか。
(宮地さん)
誰も植物語を理解したことがない、聞いたことがない、それが最大のハードルです。私たちは日本語で会話が成り立つじゃないですか。でも、植物におはようって言っても、おはようって言ってくれないんですよ。植物からの呼びかけは、、1ヶ月後に葉っぱが落ちるとか…実がつかないとか…後々にならないとわからない。その会話がその場で成り立ったらベストじゃないですか。でもそれができない、ここが最も難しいところです。そこを理解した上でなければ、DXとかスマート農業はそもそも取り入れることもできないです。
(鈴木)
植物語を理解するために何か工夫していることはありますか。
(宮地さん)
これはビジネスチャンスでしかないと思っています。ないものから生み出すのを0→1と言いますよね。農業のような一次産業に関しては、まだこれが多くあるんですよ。
事例としては、うちのAIで水やりをするシステムは、植物の「しおれ」というものをカメラで定量的に見ていて、熟練の農家さんのノウハウとかアカデミアの知識を積み込んだAIが判断して水やりを自動化しています。これが「植物の顔色を伺う」というキーワードです。人間も疲れたら顔にでたり、前かがみになったりしますよね。それを植物の場合は、「しおれ」で判断し水や肥料を調整して育てるんです。
もう一つの事例が、Stomata Scopeという装置です。葉っぱの裏にある気孔を観察することで植物の状態を解析できるのですが、今までは葉っぱを取ってきて、研究室で電子顕微鏡を用いていました。あれをただ形にしただけですが、こういうものが世の中になかった。
我々は4年かけて、現場で葉っぱを採取することなく気孔を生きた状態で測定できるようにしました。
(鈴木)
起業を決意された一番のきっかけは何ですか。
(宮地さん)
お金持ちになりたい、社長ってかっこいい、そういう子供じみた気持ちをずっと持っていたんだと思います。サラリーマン家庭に生まれたので憧れが人一倍強かったのかなと。子供の頃に思い描いていたものが、社会人になりだんだん形になってきたという感じです。
(鈴木)
AIや三次産業ではなく、農業にフォーカスして起業したのはなぜでしょうか。
(宮地さん)
数学が好きだったので本当は金融機関とか証券会社で、自分で相場を作る仕事がしたかったんです。新しい通貨とか貨幣価値を生み出したいと思っていたので、ブロックチェーンとかビットコインが出た時はすごい嫉妬しましたね。
前職の市場の競り人は、相場を作るというところで一致していたので農業界に入りました。40歳の時に起業しましたが、この年でチャレンジするなら得意なところを伸ばした方がいいと思い、この農業の世界で今やっています。
昔から言っているのが、うちは農業ベンチャーじゃなくて、八百屋ベンチャーだということです。日本も先進国も、農家さんが減っている。八百屋の目線から見ると、仕入れ先がなくなったら商売にならないでしょう。仕入れ先を増やさないと八百屋が食っていけない、そこからこの会社を作ったんです。
(鈴木)
前職の経験は生かされていますか。
(宮地さん)
むしろ前職の経験を生かすことしかしていません。Happy Qualityはスタートアップという位置づけで考えると、他にないと言えるくらい出口、売り先を持っています。だからこそうちの会社は、固い、強いと言われるんです。前職の経験を生かし、出口から入口を作るというところを逆算した会社運営をしています。
(鈴木)
これまでお仕事されている中で印象に残っている出来事はありますか。
(宮地さん)
会社を立ち上げて3年目ぐらいに、台風で6000万円くらいの被害を受け会社が潰れそうな状況でしたが、当時のメインバンクが資金を提供してくれて、持ちこたえることができました。
もう一つは、上場企業以外がチャレンジできる経済産業省の認定を貰ったことです。
経済産業省の認定事業で、農業部門からトライするのは珍しいんです。当時は資本金100万円で従業員0人でしたが、最終的に決勝戦まで勝ち上がって認定をもらうことになりました。その後、農水省から電話が来て、経産省の認定なのに農水省が連番で併記したんです。国が認定したことがない100万円会社で従業員0の会社が、省庁をまたいだ認定をいただいた。それがうちの最大の功績だと思っています。
(鈴木)
Happy Qualityという社名に込められた思いはありますか。
(宮地さん)
読んで字のごとく、幸せ品質を全ての人に届けたい、共有したいという意味ですね。
ちなみにロゴの「H」は出会いの連鎖を表しています。
(鈴木)
今後達成したい目標を教えてください。
(宮地さん)
金儲けは当たり前なんですが、そんなことよりもこの業界の意識改革をやりたいんです。
そうじゃなかったら40歳で会社は辞めないです。この業界の意識があまりにも低いから、農家も八百屋も衰退する。だから市場という舞台から離れてちびっ子会社を立ち上げて、今まで言ってきたことをただ形にしているだけなんです。
(鈴木)
若い世代に農業の魅力を伝えるとしたら、どのように表現しますか。
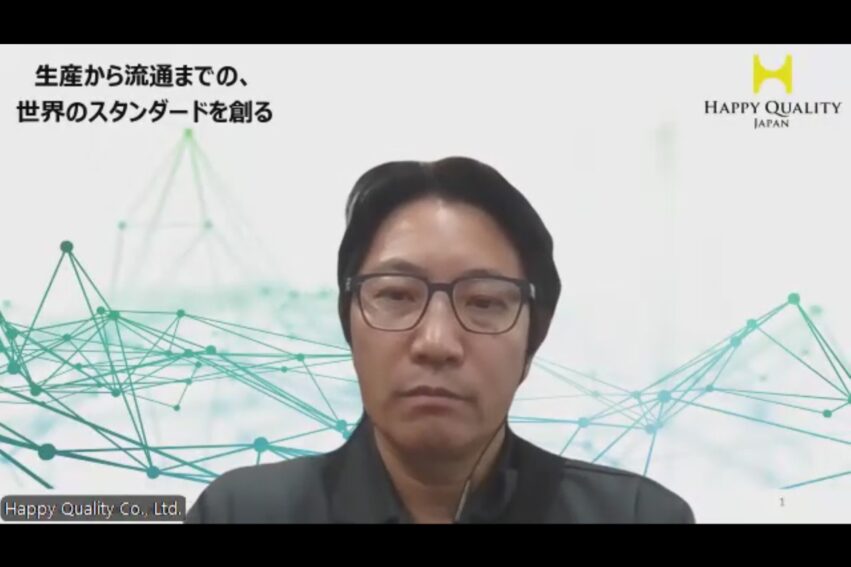
(宮地さん)
魅力しかないよってことですね。自分はあくまでも数字でビジネス的にしか語れませんが、農業はビジネスチャンスしかない、これが最大の魅力です。
さっきの気孔を観測するStomata Scopeは、子供の頃にルーペで見ていたのをただスマホで具現化させただけです。でもそれが世界でもてはやされる。我々やアカデミアが気づいていないパラメータは、沢山あるんです。研究開発の部分では永遠に終わらない課題があるということはつまり、永遠に商売が続くってことですよ。
あとはグローバルで見れば、文化、歴史、環境が全て違うでしょう。だから好みも違うわけです。つまりそこで作る技術も売る技術も千差万別、だからこの業界は終わらないんです。
(鈴木)
最後に、将来の選択に悩む学生に向けてメッセージをお願いします。
(宮地さん)
悩むなってことですね。
悩んでいるんじゃなくて、みんな知らないだけです。知らないからどうしようと自分探しの旅でわけわからなくなってるんですよ。そもそも自分のことも知らない。だから何でも飛び込んで経験すればいいですよ、若い頃の特権なんだから!
あとは信用を得たい、信頼されたいと思っても、言ってきたことを形にしないと人は信用してくれません。形という実績があるからこそ人は信用に足ると思って寄ってきてくれます。ですがこれだけだとビジネスは成り立ちません。一回売って終わり。信用されると次は、信じて頼る、これが信頼です。そうすると、コミュニティが生まれる。1対1が10になり、100になり、1000になる。そうすることで、ビジネスが動き出す。ビジネスはリピーターをいかに増やして、回すかってことなんです。実績、信用、信頼っていう順番が世の中にあることを若いうちに気づくと、とんでもない大人に化けます。
最後にもう一つ。何でも興味を持ってください。世の中にチャンスっていくらでもあるよってよく言いますよね。なんで見つからないかというと、気づかないからです。なんで気づかないかというと、考えていないからです。目の前のチャンスに気づくには考えることです。でも何を考えればいいかがわからないでしょう。だから何にでも興味を持つんです。
そして色々な人と共有してください。10人いたら十人十色の言葉があるから、いいとこどりをして考える引き出しがいっぱいできる。これから大人になって、会話をするときにその引き出しをぜひ開けてください。これが一番伝えたいことです。
インタビューを終えて
(鈴木)
画面越しでも熱量が伝わってくる楽しいインタビューでした。私は普段あまり農業に関わることがなく、ただ美味しく食べているだけの人間なので、その裏側だったり、科学とか様々な技術が融合しているのを見て目から鱗でした。本当に楽しい時間をありがとうございました!
(畠中)
農業という一次産業にビジネスチャンスが多く眠っているということにすごく納得しまして、夢があるなというふうに感じました。
それこそHappy Qualityさんの事業モデル、入口と出口を確保しているというのも、八百屋がやってることを事業モデルにしていることも、まさに形にするということを体現していて、お話を聞いて納得しました。本日は貴重なお話をありがとうございました!
以上、Happy Quality株式会社代表、宮地さんのインタビューでした。 次回もお楽しみに!

COMMENT