
こんにちは!運営の泉田です。
今回の経営者インタビューは株式会社nexfare代表の山口友也様です。
「新たな福祉を創造する」を目指し、ITとデザインをかけ合わせ、介護業界の問題に取り組んでいる「株式会社nexfare」。今回のインタビューでは、山口様の起業のきっかけや「悩んでいる学生」へのアドバイスなど、メッセージがたっぷり詰まった記事になっています。
ぜひご一読ください!
会社概要
会社名 株式会社nexfare
代表 山口友也
住所 新潟県長岡市大手通2-2-6
設立年月 2024年
事業内容 web開発、システム開発、グラフィックデザイン
URL 株式会社nexfare
インタビュー
それではインタビュースタートです。

(後藤)
ビズキャンプラスの学生のために事業内容を教えてください。
(山口様)
私たちの会社は、介護領域を中心にITを活用しているITベンチャーです。創業し2期目を迎えたのですが、1期目は介護施設に売店を作る事業をしていました。一般的にPOSレジと呼ばれるようなレジシステムをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。それを開発し、介護施設に導入していただき、施設の利用者様がいつでも好きなタイミングで欲しいものを買える環境を提供していました。現在は、少し方向性を変え、サービスを委託者様から依頼内容を受託し、アプリを開発して納品する受託事業をメインで行っています。こちらも主なターゲットは介護施設です。
(後藤)
DX事業やデザイン事業は、具体的にはどのようなことをされているのか教えてください。
(山口様)
デザイン事業で言うと、名刺を作ったり、ロゴを作ったりといった、いわゆるクリエイティブなものを作っています。そこは、一般的によくあるデザイン事業と同じです。DX事業に関しては、事例をお伝えすると、ホームページ制作や、最近納品が終わった動画研修サービスなどがあります。
介護施設の研修は、従来、職員が一箇所に集まり同じ時間に研修を受けるというスタイルが多かったようです。しかし、シフトの関係で全員が集まれない、人数が多くなれば同じ研修を繰り返し行う必要があるなどの課題がありました。そこで、動画研修サービスを当社で作らせていただきました。こちらは、ヒアリングから各施設に合わせた研修動画を作成し、納品するというサービスです。
(後藤)
介護施設や高齢者に関する事業を立ち上げるきっかけになった出来事はありますか?
(山口様)
長岡高専に在学していた3年前になりますが、きっかけは2つあります。まず祖母が認知症で、介護施設に入所していたことです。車椅子での生活に加え、認知症による物忘れもひどく、トイレの介助も必要な状態です。おばあちゃん子だった私は、大好きな祖母の元気のない様子や、家族の介護を目の当たりにし、何かできないかと思っていました。
そんな中、長岡市が運営するマッチングハブというイベントがありました。企業と学生、銀行、観光、公的機関などを繋げるイベントなのですが、そこで介護施設の方と会い、具体的な悩みを聞くことができました。介護施設の困りごとを解消する為、最初は研究という形で事業をスタートし、その後自分の会社を立ち上げたという流れです。
(後藤)
売店サービスで使用する、専用商品タグやアプリの具体的な使い方について教えてください
(山口様)
介護施設は、スペースが限られています。また、認知症の方もいらっしゃる特別な環境なので、商品を現物で置きたくないという思いもありました。この2つの観点から、壁を売店にしてしまおうと考えました。
専用の商品タグはRFIDカードというもので、Suicaのようなものです。Suicaのようなカードに商品イメージと値段を印刷して、施設の壁にかけておくだけです。施設の利用者様はそれを見て欲しいものを選び、施設の職員の方にカードを渡します。職員の方は、専用のパソコンに入っているアプリにカードを登録します。これがレジの機能を持っているわけです。専用のカードリーダーに読み込ませることで、商品を読み込み、例えば「ポテチ 1袋 200円」のように商品と値段が表示されます。そこから決済手続きを進めていくというイメージです。その後は、施設内の在庫をお渡しするという流れになります。
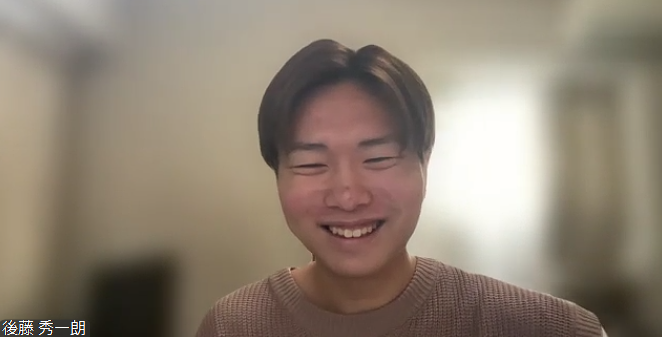
(後藤)
介護施設にも様々な種類がありますよね
(山口様)
おっしゃる通りですね。介護施設の中で一番介護度が高い方々を専門とする施設が、特別養護老人ホーム(特養)です。特養は介護度3以上でないと入所できない施設で、入所されている方は車椅子が前提だったり、寝たきりの方もいらっしゃいます。そういった方々には、私たちの売店サービスはターゲットとして適していませんでした。
そこで、ターゲットをサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と呼ばれる場所に変更しました。サ高住は、アパートに介護サービスが付いているようなイメージです。介護施設というよりは、アパートとして入居でき、その中で生活しながら介護も受けられる場所です。サ高住は、比較的介護度が低い方が入居されています。そういった方々は、外まで買い物に行くのは大変だけれど、施設内で完結できればというニーズがあります。そこでサ高住をターゲットにサービスを展開していました。
判断ができない以外にも、現金管理の問題があります。施設の利用者様の中には、現金をなくしてしまったり、誰かに取られたと言ってしまうケースもあります。現金を持ち込めない施設もあれば、持ち込みは自由ですが利用者様の管理でという施設もあります。
このような管理能力がない方もいらっしゃる状況から、私たちは決済サービスを導入しました。アプリ上で貯蓄できるようにし、毎月1回請求書を自動発行することで、施設の利用料と合算して後払いいただく仕組みです。これにより、現金をやり取りせずに商品の売買ができるようになり、どなたでも商品が買える状態を作ることができました。
他にも、実現には至らなかった構想として、アレルギー対応がありました。請求書発行の関係で、誰が何をいつ買ったかという情報を記録しているので、例えばAさんはエビアレルギーだから、かっぱえびせんを食べられないといった情報を事前に紐づけておくことで、かっぱえびせんを買おうとしたらアラートが出て「買えません」と表示されるようにする。そうすることで、属人化せずに商品の売買を安全にできるような仕組みを考えていました。
(後藤)
介護施設での売店サービスを進めていく中でうまくいったこと、大変だったことを教えてください。また、そこから工夫したことをお聞かせください。
(山口様)
施設側としては、在庫を持ちたくない、管理の手間を減らしたいというニーズがあります。しかし、在庫を少量にすると運用コストが高くなってしまいます。その対策として、コンビニと連携し、コンビニが訪問販売に行く際に、商品をリアル販売すると同時に在庫を補充していくスキームを考えた時期もありました。
うまくいった点としては、サ高住とはサービスの相性が良かった所です。例えば、特定のお客様がキャラメルを大量購入される施設がありました。その施設ではキャラメルの在庫を多くするようにしていましたね。その方は、途中で介護度が変わり、施設を退去されてしまいましたが、柔軟に対応できた部分は良かったと思っています。
一方で、この売店サービスの課題は物流でした。商品が売れる値段は限られています。コンビニでの商品価格は少し高くなっていると思いますが、せいぜいあれが限界です。物流の利益率は本当に数パーセントの世界なので、これをサービス化した際、利回りの悪さが本当にきつかったです。社会的な意義はすごくあったと個人的にも思っていますが、結論的には、経営的な部分、事業性の面で苦戦しました。
(後藤)
IT事業に方向性を変えたきっかけは?
(山口様)
なぜそうなったかというと、販売に伴い施設の方にも手間が発生します。欲しいものがあっても、今は忙しいからそんなことは考えていられないという状況です。また、サービスは良いけれど、そこにお金は割きたくないというのが結論でした。「あればいいけど、必須ではない」という状態ですね。施設側から懇願されているわけでもなく…。そこで、もっと介護施設の余裕を作らないとダメだという考えに至り介護施設のDX化という方向へシフトしていきました。
(後藤)
売店サービスを導入する中で、利用者の方からの反響を含め、どんな時にやりがいを感じましたか?
(山口様)
施設に行った際に「これは次の社会を作っていくんだね」「すごく面白いね」「ありがとう」と評価をたくさんいただいたことです。本当に嬉しかったです!ただ、評価と、利益、サービス導入は全く別物でした。社会的な意義は評価していただけましたが、そこから「うちに導入したい」という具体的な話には、なかなか繋がらなかったのが現実です。そこが、事業の難しさを感じた部分でもあります。
(後藤)
山口代表ご自身のことについても聞かせてください。経営者として日々意識していること、習慣があれば教えてください。

(山口様)
意識しているというか、自然とそうなったことで言うと、失敗の許容レベルがものすごく上がりましたね。以前は、他の人と比べて「なんで自分はこんなにできないんだろう」と落ち込むこともありましたが、今はできないことの方が多いのは当然だと考えるようになりました。
できないことに直面した時も、もちろん全力で取り組み、反省もしますが、それ以上に「ここからこういう学びが得られた」と意識できるようになりました。この1年間で、これは大きな収穫だったと思っています。それができないと、ずっと落ち込んでいる状態になってしまいますから。そうではなく、次に活かせるように意識することは、習慣づいているかなと思います。
(後藤)
新たな福祉の形としてネクストウェルフェアを掲げていますが、福祉や介護施設の今後のあるべき姿のお考えを教えてください。
(山口様)
これが正解かどうかは数十年後に分かると思うのですが、もっと生活の質を重視すべきだということです。介護領域は、まだまだ受動的な状態が多く、レクリエーションも「皆さん一緒に踊りましょう!」のように集団での体操が行われています。
もっと個人のやりたいことができる環境を作っていくことで、帰ってきた後に元気がなくなるような状態をなくせると思っています。介護施設や病院で、本来やりたいことがどんどん抑制されていった結果、やりたいという感情も薄れていき、活力がない状態になっているのではないかと考えています。そこを何とかしたい。入所者の方々が活力ある状態を取り戻せるようにしたいです。例えば、「花を育てる」「お酒を楽しみたい」など、許される範囲で自分のやりたいことが叶えられる環境。その場所が介護施設というような状況にしていきたいですね。なので、私たちが目指す「新しい福祉」では、日常生活がより豊かになっているはずです。
(後藤)
ビズキャンプラス(社会へ羽ばたく準備中)の学生たちに、学生のうちにやっておいてほしいこと、があればアドバイスをお願いします。
(山口様)
昨年1年間、メーカーズユニバーシティという起業家の方々の集まりに参加して気づいたことがあります。今、学生で悩まれている方はたくさんいると思いますが、それが最も正常な状態だということです。その状態を受け入れることが、すごく大事だと思います。
焦ったり、劣っていると感じるのではなく、自分が今迷っている状態は正しい道筋であると認識すること。これは当たり前のことを言っているように聞こえるかもしれませんが、これをちゃんと認識できているかどうかで、自分の状態や将来の見え方が大きく変わってきます。
自分のことをちゃんと理解できているかどうかが、どんな道に進むにしても大きな影響を与えます。起業することが正義だとは思っていませんし、他にも色々な道があると思っています。その中でも、自分のことを理解できている人の方が強いと思います。自分のことを理解するための時間が大学生活だと思うので、その時間をしっかり使い、正常に迷ってください。
たくさん迷ってください。迷うことを放棄したら終わりです。特に考えたくないから、家から近いから、という理由で就職先を選ぶのは良くないと思います。しっかりと向き合って考えることが大切です。その選択でより良い道が開けると思います。
インタビューの感想
(後藤)
話していて感じたのは人生100年時代と呼ばれているので、介護の重要性がかなり高くなってきていることです。今回のお話の中で、高齢者の方ができることが少なくなったり、暗い部分が自分の中で見えてきたりするというのがあったとしても、サポートのやり方次第で楽しくできることを実感しました。これは自分たちにも言えることだと思います。日々をちょっとプラスアルファ楽しくするという面では、別にどの世代関係なく、生活の中に一手間加えることで、ちょっとした何気ない生活に楽しさを見出すことができると思います。私自身もやらなきゃいけないことだなと感じましたし、私もそういうことは気を引き締めてやっていきたいなと思いました。
以上、株式会社nexfare代表の山口友也様のインタビューでした!
次回もお楽しみに~

COMMENT