
こんにちは!
ビズキャンプラス運営の泉田です。
今回は、株式会社TOMUSHI代表取締役社長の石田陽佑さんへインタビューをさせていただきました!カブトムシの力を活用して有機廃棄物問題と食料不足問題の解決に取り組む、秋田県発の昆虫バイオスタートアップ「株式会社TOMUSHI」。ここには壮大な社会課題解決への想いと、波乱万丈な人生ストーリーがありました。
失敗を恥ずかしがらずにオープンにすることで、掴んだチャンス!ビジネスから地方創生を目指す壮大なビジョン!
将来に悩む学生の皆さんにとって、勇気をもらえるお話をお聞きしました。
会社概要
会社名 株式会社TOMUSHI
代表 石田陽佑
住所 秋田県大館市
設立年月 2018年
事業内容 カブトムシによる循環農業
有機廃棄物処理
代替タンパク質開発
医薬品原料研究
URL 株式会社TOMUSHI
インタビュー
それではインタビュースタートです。

(横井)
ビズキャンプラスの学生に向けて、事業内容のご紹介をお願いします。
(石田さん)
会社名は「株式会社トムシ」です。なぜトムシかというと、株式会社を省略形にして「(株)トムシ」になるという、単純な理由でつけました。ロゴは、カブトムシとクワガタの二股の角を表していて、循環で途切れないマークを表現しています。
現在、会社は7期目で、事業内容は「カブトムシによる循環農業」です。具体的には、未利用の有機廃棄物や生ごみをカブトムシの餌にし、カブトムシが排泄した糞を有機肥料として農業に再利用します。また、カブトムシの幼虫は粉末に加工され、代替タンパク源や医薬品の原料として活用されています。今年はすでに600トン分の幼虫が発注されるなど、事業は順調に拡大しています。
(横井)
カブトムシとクワガタでは、事業に関わる違いはありますか?
(石田さん)
カブトムシとクワガタは生態が大きく異なり、産業利用においてはカブトムシの方が圧倒的に効率的です。カブトムシは天敵が多い環境で生きるため、集団で生活し、卵を多く産む習性があります。人工的に飼育すれば天敵がいなくなるため、1匹から100匹程度まで増やすことができ、非常に高い生産効率を実現できます。また、餌も腐敗した有機廃棄物を利用できるため、資源の有効活用にも繋がります。
一方、クワガタは天敵が少ない場所で育つため、産卵数が少なく、共食いの習性もあるため大規模生産には向きません。さらに、餌も腐る直前のものしか食べないため、産業としての利用は難しいのが現状です。
(鈴村)
カブトムシで有機廃棄物を処理するアイデアは、どのような背景から生まれたのでしょうか?
(石田さん)
最初は銀行や祖父母から合計2,000万円ほど借りて、双子の兄とカブトムシの事業を始めました。しかし、飼育方法の不備で多くのカブトムシを死なせてしまい、資金難に陥りました。その窮地を救ったのは、地元の銀行員との対話でした。廃棄物をカブトムシの餌にできないかというアイデアから、有機廃棄物を有効活用できることが判明しました。これをきっかけに、事業は単なるカブトムシ販売から、増え続けるゴミ問題とタンパク質不足という地球規模の課題を解決する「循環型事業」へと発展しました。
(鈴村)
大変な状況がチャンスに変わったきっかけや理由は何だったと思われますか?
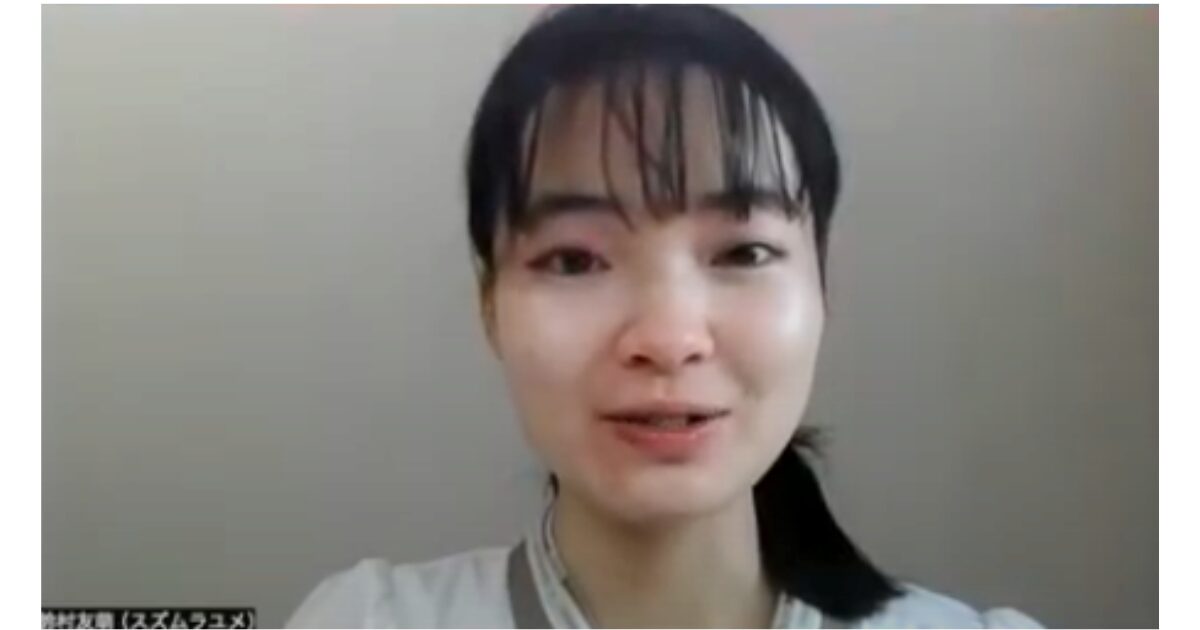
(石田さん)
私はこれまでも多くの失敗をしてきましたが、常に「面白くない失敗はしないようにしよう」と心がけています。できるだけ大きなチャレンジをすれば、話のネタになるからです。会社が潰れる確率は90%以上という状況でしたが、「最悪、潰れてもなんとかなるだろう」と思っていましたし、知り合いの経営者や銀行員の方にも「今やばいんですよ、社員もみんな辞めてしまって一人なんです」という話をよくしていました。
すると、話を聞いてくれた人たちが、「こんな解決策があるんじゃないか」「ちょっとお金を支援しようか」と言ってくれるようになりました。ただ家の中で悩んでいても何も解決しません。だから私は、ミスや大きな失敗をした時は、多くの人に「これやばくないですか?めっちゃ面白くないですか?」と話しています。結果、色々な人と繋がることができ、人に恵まれたと思います。
(鈴村)
事業を進めるにあたっての原動力は何だと思われますか?
(石田さん)
私の起業の原動力は、家族と地元への深い思いです。中学時代に家出して以来、母方の祖父母に育てられ、大学の学費から起業の資金まで、すべてを援助してもらいました。祖父母は代々受け継いできた土地や不動産まで売却して応援してくれたため、この会社を通じて恩返しをしたいと強く思っています。
もう一つの原動力は、地元・秋田県大館市の最年少市長を務める双子の兄です。もともと二人で起業しましたが、祖父母が地元を離れたがらないことから、兄は政治の力で大館を変えることを決意しました。そして、兄が大館で市政を担う一方、私は秋田県北部で史上初の上場企業を創出し、地域経済を活性化させることを目標としています。
(横井)
起業する際に不安はありませんでしたか?

(石田さん)
実際不安はありました。ただ、不安な気持ちを乗り越えるために、最悪のケースを想定し、自己破産経験者の話を聞いたり弁護士に相談したりしました。その結果、日本では自己破産が再チャレンジの機会として機能する制度であることを理解し、恐怖がなくなりました。ゲームの「桃鉄」に登場する「自己破産カード」のように、事業の失敗で負った借金はリセットされ、また一からやり直せます。このことに気づいてからは、「思い切ってチャレンジすべきだ」と前向きな姿勢に変わりました。
(泉田)
好きなことを仕事にするための秘訣や、就職活動におけるコツがあれば教えていただけますか?
(石田さん)
弊社の社員の中にも、カブトムシが好きな人とそうでない人がいます。カブトムシが好きな人は、カブトムシの現場ではない仕事において、成果が上がらないことがあります。なので、好きな分野を選ぶということが大切です。また、仕事をする中で、「どういう仲間たちと働きたいか」というのも大事だと思います。
私たちの会社には、財務など様々な仕事があります。しかし、みんなの根底にあるキーワードは「カブトムシ」なので、そこから派生する仕事はすべて「カブトムシのため」という共通認識が社内にはあります。
「好きを仕事にしよう」と入社してみたら、全然違う部署に飛ばされて辞めてしまう、というケースもあると思いますが、大元の部分で好きなものがあって、そこで仕事をする方が楽しいという意識はすごく大事だと思います。
これは、取引先を選ぶ際にも当てはまります。創業者がなぜその事業を始めたのか、そのストーリーに触れることで、仕事への熱意が伝わってきます。そうした想いを知ることで、相手の会社に対する理解が深まり、より丁寧な関係を築くことができると考えています。
(泉田)
創業者の思いを図る上で、石田さんが意識していることがあればお伺いしてもよろしいですか?
(石田さん)
私が重要だと考えているのは、創業者の想いが社員にどれだけ浸透しているかです。私自身も多くの苦労を経験してきましたが、失敗談を包み隠さず共有し、なぜ事業を始めたのかを会社のビジョンとして明確に示していることが大切だと思っています。
そして、そのビジョンを社員一人ひとりが深く理解し、共感しているかどうかが、会社の方向性を左右します。これは、兄が市長を務める大館市が掲げる「シビックプライド」と同じで、私たちが「TOMUSHI」に誇りを持てる「トムシプライド」を育むことが不可欠です。「どんな会社ですか?」と聞かれたときに、「創業者の想いに共感して入社した」と誰もが言えるような会社を目指しています。
(横井)
学生時代にやっておいた方がいいことや、起業する上で身につけてよかったと思うことについて教えてください。
(石田さん)
私が考えるのは、コミュニケーション能力です。社長の役割は、仕事を完璧にこなすことではなく、信頼できる仲間を集めることだからです。私が周りに助けてもらいながら事業を続けてこられたのも、周りの人に「この人を助けてあげたい」と思ってもらえるような関係性を築くことができたからだと思います。
次に不可欠なスキルは財務の知識です。会社は、儲かっていても潰れる可能性がありますし、赤字でも耐えられる場合があります。これは、キャッシュフローを正確に把握しているかどうかにかかっています。特に、会社を始めてから財務や経理、数字面はかなり勉強しました。
(鈴村)
好きなことを仕事にする魅力と、もし覚悟があったのであれば、それはどこから来たのかを伺いたいです。
(石田さん)
「好きなこと以外やらない」ことです。好きなことを仕事にすると、責任が伴い、嫌な仕事も引き受けざるを得なくなります。創業当初は私もそうでしたが、「好きなことを仕事にしたせいで、それが嫌いになってしまうのは避けたい」と強く思っていました。
そのため、私は自分がやりたくない仕事を社員募集の要項に入れるようにしています。例えば、私が苦手でやりたくない財務や会計、税務の仕事を募集すると、それが得意で好きな人が集まってくれます。そうして、各々が好きなことを担当することで、会社全体からストレスがなくなります。今では、私は好きなことだけに集中でき、ストレスなく、楽しんでいます。「嫌なことをやらない」という意識が、私にとって非常に大切です。

(鈴村)
今後の事業展開について教えてください。
(石田さん)
現在、カブトムシを活用した事業は、次のフェーズに進んでいます。国内に約100カ所の拠点を設け、大量生産体制が整い、カブトムシに付加価値をつけることを目指しています。単にペットとして売るのではなく、カブトムシを原料として加工し、成分分析を通じて用途を広げ、より高く販売するための研究開発を進めています。次の段階として、国内で確立した「ゴミを資源に変え、高付加価値化する」というビジネスモデルを海外に展開する計画です。特に環境問題が深刻な東南アジア市場をターゲットとしており、ゴミを焼却せずに資源化するプラントの導入を目指しています。
しかし、海外では文化の違いからカブトムシがゴキブリと混同されることもあります。そのため、海外市場では「かっこよさ」ではなく、カブトムシの機能性や生活への貢献度といった実用的な魅力を伝える必要があります。
最終目標は、東北・秋田県北エリアから初の上場企業となり、そこで得た資金でグローバル展開を加速させることです。そして、将来的には世界中の人々がカブトムシを「地球に役立つ存在」として認識する社会を目指していきたいです。
(泉田)
石田さんの生き方について教えてください。
(石田さん)
私の生き方の根底にあるのは、「恥ずかしがらずに話そう」という祖父母の教えです。厳しい父とは違い、祖父母は私の失敗を笑い飛ばし、「ダメでもともとなんだから、次頑張れよ」といつも励ましてくれました。この経験から、私は社会に出ても、自分の失敗を否定的に捉える人とは距離を置くようにしています。彼らは成長意欲に欠けており、私のような挑戦を続ける人たちとは人種が違うと考えているからです。
失敗を話した時に、応援や協力を惜しまない仲間こそ、末永く付き合うべき相手だと思います。就職活動や職場の上司に対しても同じで、失敗をただ叱るのではなく、次への改善策を一緒に考えてくれる人かどうかを重視しています。否定的な意見を言われても、悔しい気持ちはありますが、それをバネにして「話が通じない人もいる」と割り切ることで、自分の精神的なダメージを防ぎ、より良い人間関係を築くことにつながると思います。
インタビューを終えて
(横井)
「好きを仕事に」するというお話がすごく良いな、と感銘を受けました。やはり好きなことを仕事にすると、モチベーションも上がりますし、何においても原動力になることが増えるのだろうなと感じたので、私も就職活動する上で大事にしたいと思いました。
(鈴村)
今まで、成功を掴むためには、マイナスなことや失敗は隠して何とかするものだ、というのが自分の固定観念としてありました。しかし、逆に失敗を話すことによってチャンスを掴むことができる、という逆転の発想があるのだと感銘を受けました。今までマイナスなことがあったら、反省だけで終わっていましたが、それをもっと他の人に話すことでうまくいくというのは、石田さんの人徳の深さだと思いますし、そういう人徳があるからこそ、事業がうまくいったのだろうなと強く感じました。貴重なお話、ありがとうございました。
以上、株式会社TOMUSHI代表の石田さんのインタビューでした!
次回もお楽しみに!

COMMENT